ニュース


建設業に助成金・補助金はある?申請方法や必要書類も解説
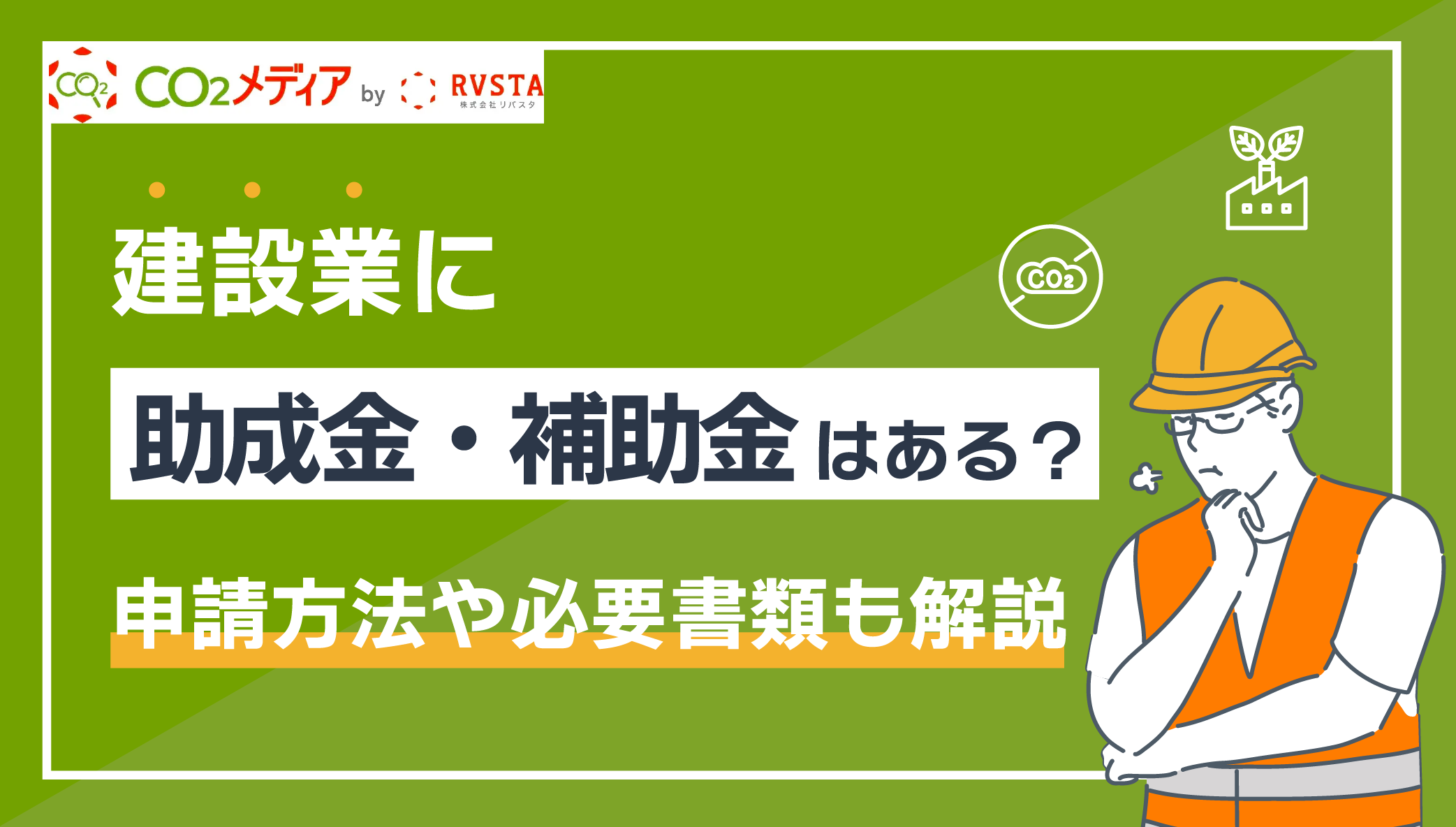
建設業を営むうえで、人手不足や設備投資に関する問題は、多くの人が直面します。その悩みは、助成金や補助金を利用することで解決できるかもしれません。
そこで、本記事では、建設業の助成金・補助金を合計で八つ紹介しています。さらに、申請方法や必要書類についても解説します。条件さえ満たしていれば、すぐにでも申請が可能ですので、ぜひ参考にしてください。
建設業における助成金・補助金の重要性とは?

そもそも、助成金・補助金とは一体何なのでしょうか。また、その効果的な活用法にはどのようなものがあるのでしょうか。簡単に解説します。
助成金・補助金
助成金と補助金は、企業や個人が行う事業やプロジェクトへの経済的な支援です。国をよりよくする事業のサポートを目的に、国や地方自治体、公的機関が資金を提供しています。
補助金は経産省系、助成金は厚労省系。経産省は技術開発、厚労省は雇用が主な対象になっています。具体的には、新しい技術の研究開発や雇用の拡大、事業の持続性の確保など、さまざまな目的で設けられています。建設業は、経済の発展や社会基盤の整備に欠かせない産業です。そのため、助成金・補助金を提供することで、建設業が抱える問題を解決しようとしているのです。
助成金・補助金の効果的な活用法
効果的に活用するためには、まず自社の事業活動がどのような助成金・補助金の対象となるのかを正しく理解しましょう。最適な助成金・補助金を見つけたら、要件や応募条件を確認して申請手続きへと移ります。
助成金や補助金を受け取った後には報告義務が発生するため、どのような報告が必要となるのかは必ずチェックしましょう。報告の負担も考慮して助成金を選ぶ必要があります。
ルールをしっかりと守りつつ、助成金・補助金を利用することで事業活動の安定化や、新技術の導入、雇用の拡大など多くのメリットを得られます。また、助成金・補助金の活用は企業の信頼性やブランド力を向上させる効果もあります。
建設業における5つの助成金【令和5年度】

ここからは、建設業における5つの助成金を紹介します。
具体的には、下記の建設事業者向けが3つ、建設事業主団体・職業訓練法人向けが2つの合計5つです。
建設事業者向け:3つ
トライアル雇用助成金
人材確保等支援助成金
人材開発支援助成金
建設事業主団体・職業訓練法人向け:2つ
人材確保等支援助成金
人材開発支援助成金
3つの助成金:建設事業者向け
トライアル雇用助成金
トライアル雇用助成金は、35歳未満の若年者や女性を一定期間、試行雇用する中小建設事業主を対象とし、雇用の手助けを行うものです。支給額や条件は以下の表のとおりです。
| 支給額(1人あたり) | 就労日数が75%以上:月額4万円
50%以上75%未満:月額3万円 25%以上50%未満:月額2万円 0%以上25%未満:月額1万円 |
| 給付条件 | ①母子家庭の母、父子家庭の父、35歳未満の若年求職者などをトライアル雇用
②雇用した人員に建設工事現場で作業を行わせる ※その他諸条件あり |
| 支給対象職種 | 左官、大工、鉄筋工、配管工など(設計や測量、経理、営業などの職種は助成対象外) |
| 最高支給期間 | 3ヶ月 |
支給額は、トライアル雇用した労働者が1ヶ月で予定していた就労日数のうち、実際に何日就労したかどうかで変動します。
参照:トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)|厚生労働省
人材確保等支援助成金
建設業界では、魅力ある職場環境を整備することで、若年者や女性の入職や定着を目指す取り組みに力を入れています。人材確保等支援助成金は、そのような取り組みを支援する目的で設けられています。
全部で8つのコースが用意されており、建設事業者が活用できるコースは以下のとおり。
| コース | 支給額 | 主な要件 |
| 雇用管理制度助成コース | 目標達成で57万円 | ◯雇用管理制度の導入
◯離職率目標達成 |
| 人事評価改善等助成コース | 目標達成で80万円 | ◯従業員の賃金アップを含む人事評価制度を導入 |
| 若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野) | <要件①の場合>
中小建設事業主:支給対象経費の3/5
中小建設事業主以外の建設事業主:支給対象経費の9/20
<要件②の場合> 支給対象経費の2/3 |
◯以下2つのいずれか
①若年および女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行う
②建設工事における作業についての訓練を推進する活動を行う |
| 作業員宿舎等設置助成コース(建設分野) | <要件①の場合>
支給対象経費の2/3
<要件②の場合> 支給対象経費の3/5
<要件③の場合> 支給対象経費の1/2
<要件④の場合> 作業員宿舎:建設労働者1人あたり25万円
賃貸住宅、作業員宿舎:支給対象費用の2/3 |
◯以下4つのいずれか
①岩手県、宮城県、福島県に所在する作業員宿舎、作業員施設、賃貸住宅を賃借した中小建設事業主
②自ら施工管理する建設工事現場に女性専用作業員施設を賃借した中小元方建設事業主
③認定訓練の実施に必要な施設や設備の設置又は整備を行った広域的職業訓練を実施する職業訓練法人
④石川県に所在する作業員宿舎、賃貸住宅、作業員施設を賃借した中小建設事業主 に対して助成します。 |
| 外国人労働者就労環境整備助成コース | 支給対象経費の1/2(上限57万円)
※賃金要件を満たした場合は2/3(上限72万円) |
◯就労環境整備措置の導入・実施
◯離職率目標の達成 |
| テレワークコース | 機器等導入:1企業あたり、支給対象となる経費の50%
目標達成:1企業あたり、支給対象となる経費の15% ※賃金要件を満たす場合25% |
◯評価期間において、1回以上、テレワーク実施対象労働者全員がテレワークを実施
◯評価時離職率が、計画時離職率以下であること |
活用できそうなコースを検討し、詳細を確認してみてください。
人材開発支援助成金
人材開発支援助成金は、建設業界の人材育成と技能の維持・向上のために導入された助成金です。研修にかかる経費や研修期間中の賃金を一部補助するために設立されました。
人材開発支援助成金では、全部で以下7つのコースが用意されています。
- 人材育成支援コース
- 教育訓練休暇付与コース
- 人への投資促進コース
- 事業展開等リスキリング支援コース
- 建設労働者認定訓練コース
- 建設労働者技能実習コース
- 障害者職業能力開発コース
建設事業者向けに提供されているのは、「建設労働者認定訓練コース」「建設労働者技能実習コース」の2つです。以下の表に支給額や主な要件をまとめたので、参考にしてみてください。
| コース | 支給額 | 主な要件 |
| 建設労働者認定訓練コース | 経費助成:支給対象経費の1/6
賃金助成:認定訓練を受講した労働者1人1日あたり3,800円(1事業年度あたり上限1,000万円)
生産性向上助成:認定訓練受講者1人あたり1,000円 |
◯都道府県から認定訓練助成金の交付を受ける
◯雇用する建設労働者に認定訓練を受講させる ◯受講中も賃金を支払う |
| 建設労働者技能実習コース | 経費助成:支給対象経費の最大3/4
賃金助成:労働者1人1日あたり7600円〜9405円
賃金向上助成・資格等手当助成:経費助成を受けている場合は支給対象費用の20分の3、賃金助成を受ける場合は1750〜2000円/日 |
◯雇用する建設労働者に技能実習を受講させる
◯受講中も賃金を支払う |
どちらのコースも人材育成のために行う訓練や技能実習に対して助成されます。受講中は労働時間として換算され、賃金を支払う必要がある点に注意しましょう。
2つの助成金:建設事業主団体・職業訓練法人向け
人材確保等支援助成金
建設事業主団体・職業訓練法人向けに提供される人材確保等支援助成金には、主に3つのコースが活用可能です。
| コース | 支給額 | 主な要件 |
| 建設キャリアアップシステム等普及促進コース | 中小建設事業主団体:支給対象経費の2/3
中小建設事業主団体以外の建設事業主団体:支給対象経費の1/2 |
◯建設事業主団体が中小構成員等に対して建設キャリアアップシステム(CCUS)関連の支援事業を実施 |
| 若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野) | <要件①の場合>
中小建設事業主団体:支給対象経費の2/3
中小建設事業主団体以外の建設事業主団体:支給対象経費の1/2
<要件②の場合> 支給対象経費の2/3 |
◯以下2つのいずれか
①若年および女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行う
②建設工事における作業についての訓練を推進する活動を行う |
| 作業員宿舎等設置助成コース(建設分野) | <要件①の場合>
支給対象経費の2/3
<要件②の場合> 支給対象経費の3/5
<要件③の場合> 支給対象経費の1/2
<要件④の場合> 作業員宿舎:建設労働者1人あたり25万円
賃貸住宅、作業員宿舎:支給対象費用の2/3 |
◯以下4つのいずれか
①岩手県、宮城県、福島県に所在する作業員宿舎、作業員施設、賃貸住宅を賃借した中小建設事業主
②自ら施工管理する建設工事現場に女性専用作業員施設を賃借した中小元方建設事業主
③認定訓練の実施に必要な施設や設備の設置又は整備を行った広域的職業訓練を実施する職業訓練法人
④石川県に所在する作業員宿舎、賃貸住宅、作業員施設を賃借した中小建設事業主 に対して助成します。 |
人材開発支援助成金
建設業界の人材育成と技能の維持・向上のために導入された助成金です。概要については、「3つの助成金:建設事業者向け/人材開発支援助成金」で先述した通りです。建設事業主団体であっても活用可能な助成金となっているため、確認してみてください。
建設業における3つの補助金【令和5年度】
建設業における、次の3つの補助金を紹介します。
IT導入補助金
ものづくり補助金
事業再構築補助金
IT導入補助金
IT導入補助金は、中小企業や小規模事業者の労働生産性を高めるためのものです。具体的には、業務の効率化やDX(デジタルトランスフォーメーション)への取り組みに必要なITツールの導入に補助金が提供されます。
IT導入補助金には、導入するITに応じて4つの枠が設けられています。具体的には、以下の表のとおり。
| 種類 | 支給額 | 主な要件 |
| 通常枠 | 5~450万円(補助率は1/2以内) | ◯事業のデジタル化を目的としたソフトウェアやシステムの導入 |
| セキュリティ対策推進枠 | 5~100万円(補助率は1/2以内) | ◯サイバーインシデントに関するリスク低減策を実施 |
| インボイス枠
(インボイス対応類型) |
インボイス制度に対応した会計・受発注・決済ソフトの導入:最大350万円(補助率は3/4以内、4/5以内、2/3以内のいずれか※事業規模や機能で変動)
PC・タブレット等の導入:最大10万円(補助率は1/2以内)
レジ・券売機等の導入:最大20万円(補助率は1/2以内) |
◯インボイス制度に対応した会計ソフトやPC・ハードウェア等の導入 |
| インボイス枠
(電子取引類型) |
最大350万円(中小企業/小規模事業者等は補助率2/3以内、その他は1/2以内) | ◯インボイス制度に対応した受発注システムの導入 |
まずは、通常枠です。この通常枠では各企業に合ったITツールの導入を支援しています。具体的な補助金額は最大450万円です。なお、補助率は半分以内に設定されています。
ものづくり補助金
ものづくり補助金は、中小企業庁の新製品やサービスの開発、また生産方法の改善をサポートするための補助金です。この補助金は、5つのカテゴリーに分けられます。
通常枠では、新しい製品やサービスの開発、または提供方法の改善のための投資をサポートしています。補助額は従業員の数によって異なりますが、最低で100万、最大で1,250万円です。補助率は1/2~2/3です。
回復型賃上げ・雇用拡大枠は、賃金増加や雇用の拡大を目指す事業者のための補助金です。補助額は最低で100万、最大で1,250万円で、補助率は2/3に設定されています。
デジタル枠では、DXの推進をサポートしています。こちらも、補助額は最低100万、最大で1,250万円、補助率は2/3となっています。
グリーン枠は、温室効果ガスの削減など脱炭素に取り組む企業の取り組みを支援しています。補助額は最低で100万、最大で3,000万、補助率は2/3です。
最後に、グローバル市場開拓枠では、海外展開を目指す事業者への補助を行っています。こちらも最低で100万、最大3,000万円までの補助が可能です。しかし、補助率は基本的には1/2です。ただし、一定の条件を満たすと2/3まで上がります。
参照:公募要領について|ものづくり補助事業公式ホームページ ものづくり補助金総合サイト
事業再構築補助金
事業再構築補助金は、新型コロナウイルスの影響を受けた中小企業や個人事業主を支援する目的で設けられました。この補助金を受け取るための主な条件として、2020年4月以降の6ヶ月のうち、任意の3ヶ月の売上がコロナ発生前の同時期と比べて一定の減少があること、そして事業再構築に関する計画を策定していることが挙げられます。
補助金の金額や補助率は従業員の数に応じて変わります。通常の成長枠では、最低100万、最大で7,000万円までの補助金が提供されます。補助率は1/2~2/3です。さらに、特定の枠には最大1億円の支援が行われることもあります。
※注釈
- グリーン成長枠:グリーン成長戦略に掲げられた課題解決にあわせた人材育成を行う
- 卒業促進枠:補助事業終了後3〜5年で中小企業・特定事業者・中堅企業の規模から卒業する
- 大規模賃金引上促進枠:補助事業終了後3〜5年の間に最低賃金や従業員数を一定以上引き上げる
- 産業構造転換枠:衰退が見込まれる業種や地域にて一定の条件を満たす
- 最低賃金枠:最低賃金や売上に関する一定の条件を満たす
- 物価高騰対策・回復再生応援枠:中小企業活性化協議会等から支援を受けて再生計画等を策定している
建設業の助成金・補助金の申請方法とは?
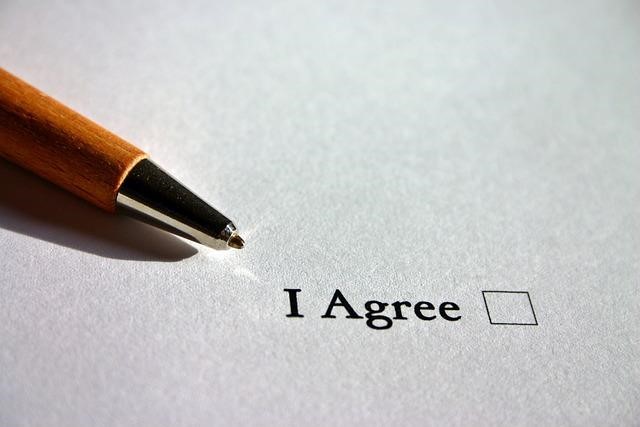
助成金や補助金の申請方法についてです。まずは、関連する各ホームページを確認することが必要です。インターネットで公開されている情報を通じて、自社が助成や補助の対象となるのか、どのような条件や基準が設定されているのかをきちんと把握しましょう。
また、助成金や補助金ごとに異なる申請方法を取っている可能性があるため、注意が必要です。例えば、申請書類を印刷して手書きで記入し、郵送する必要がある場合もあれば、電子データとして送信する方法を採用している場合もあります。事前にしっかりと確認してから申請の手続きを進めることが重要です。
建設業の助成金・補助金の申請に必要な書類とは?
助成金や補助金の申請に必要となる書類に関しても、それぞれのホームページから確認することができます。多くの場合、申請先の機関から書類のフォーマットが提供されています。申請の手続きは、フォーマットに沿って情報を記入します。
また、どのように書類を記入すればよいかの参考となる記入例や見本が提供されていることも多いです。それらを参照しつつ、誤った情報を記載しないように注意しながら記入を進めましょう。
助成金・補助金では「脱炭素の取り組み」が重要視される可能性がある

気候変動の対応策として、脱炭素の取り組みが世界中で行われています。日本国内でも、企業や事業者の脱炭素の取り組みが、助成金や補助金の評価基準として取り入れられることが増えてきました。
具体的には、CO2排出量の削減、再生可能エネルギーの導入、エネルギー効率の向上など、環境を守るための取り組みが特に評価される傾向にあります。このため、助成金や補助金の申請時に、脱炭素の取り組みをアピールできれば、採用されやすくなる可能性があります。
まとめ

建設業には、従業員の確保や成長、または事業の改善のために活用できる助成金や補助金が数多く用意されています。具体的には、トライアル助成金、人材確保等支援助成金、人材開発支援金などがあります。また、IT導入補助金やものづくり補助金、事業再構築補助金なども注目されています。
また、環境問題に対する取り組みとして、建設業でも「脱炭素」が重要になっています。その実践例も紹介しました。こういった企業の取り組みを参考に、自社では脱炭素に向けて何ができるのかを考えてみましょう。その際、活用できそうな助成金・補助金についても調べてみるといいでしょう。
建設業界では、入札段階や工事成績評点で施工時や竣工後の建築物においてCO2排出量の削減が評価され、加点につながる動きが生じています。また、建設会社からCO2排出量を開示し削減方針を示さないと、発注者であるデベロッパーから施工者として選ばれにくくなる状況も起きており、建設会社にとってCO2排出量の管理・削減は喫緊の課題です。
リバスタでは建設業界のCO2対策の支援を行っております。新しいクラウドサービス「TansoMiru」(タンソミル)は、建設業に特化したCO2排出量の算出・現場単位の可視化が可能です。 ぜひこの機会にサービス内容をご確認ください。

この記事の監修

リバスタ編集部
「つくる」の現場から未来を創造する、をコンセプトに、
建設業界に関わる皆さまの役に立つ、脱炭素情報や現場で起こるCO2対策の情報、業界の取り組み事例など、様々なテーマを発信します。
「つくる」の現場から未来を創造する、をコンセプトに、
建設業界に関わる皆さまの役に立つ、脱炭素情報や現場で起こるCO2対策の情報、業界の取り組み事例など、様々なテーマを発信します。
本ウェブサイトを利用される方は、必ず下記に規定する免責事項をご確認ください。
本サイトご利用の場合には、本免責事項に同意されたものとみなさせていただきます。当社は、当サイトに情報を掲載するにあたり、その内容につき細心の注意を払っておりますが、情報の内容が正確であるかどうか、最新のものであるかどうか、安全なものであるか等について保証をするものではなく、何らの責任を負うものではありません。
また、当サイト並びに当サイトからのリンク等で移動したサイトのご利用により、万一、ご利用者様に何らかの不都合や損害が発生したとしても、当社は何らの責任を負うものではありません。







